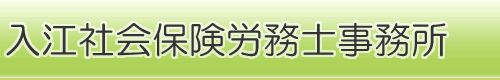今回は、今後変わるパート職員の社会保険の加入要件に関するご相談です。
当院の職員数は65人であり、週の所定労働時間が20時間以上のパート職員は社会保険に加入しています。
今後、社会保険の加入要件が変更になると聞きましたが、どのような内容でしょうか?
2025年6月に成立した年金制度改正法では、パート職員等の社会保険の加入要件の一つである、「月額賃金が88,000円以上であること」が撤廃されることになりました。
そのほかにも、社会保険の適用拡大として、パート職員等が社会保険に加入する事業所規模の要件が、いずれ撤廃されることも決まっています。
 現在、正職員のほか、週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正職員の4分の3以上であるパート職員等は、社会保険に加入することになっています。
現在、正職員のほか、週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正職員の4分の3以上であるパート職員等は、社会保険に加入することになっています。
また、週の所定労働時間等が正職員の4分の3未満であっても、職員数51人以上の事業所に勤務し、次の4つのすべての要件を満たすパート職員等は、短時間労働者として、社会保険に加入します。
- ① 週の所定労働時間が20時間以上であること
- ② 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
- ③ 月額賃金が88,000円以上であること
- ④ 学生ではないこと
2025年6月に成立した年金制度改正法により、1.の「③月額賃金が88,000円以上であること」という賃金要件が撤廃されることになりました。
施行日は確定していませんが、2025年度の地域別最低賃金が発効されることに伴い、すべての都道府県で週20時間以上勤務すれば、月額賃金が88,000円以上となる水準となり、実質的には廃止と同様の状況となります。
年金制度改正法では、短時間労働者として社会保険に加入する事業所規模(職員数51人以上)の要件が2027年10月以降、段階的に拡大され、2035年10月には撤廃されることになっています。
具体的には、職員数について2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へ拡大され、2035年10月に撤廃となります。なお、この職員数とは、事業所における厚生年金保険の被保険者数をいいます。
パート職員によっては、社会保険料の負担を避けるために週の労働時間数を減らす、いわゆる「働き控え」を選択する人もいます。
社会保険の加入対象となるパート職員には、加入による手取り額や保障の変化についても説明し、今後の働き方の希望を確認しておくことが重要となります。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
- 人事労務Q&A 〜体調不良で欠勤が続く職員に対する休職発令〜2025/10/31
- 人事労務Q&A 〜育児と仕事の両立のために柔軟な働き方を実現できるようにするための法改正〜2025/09/30
- 人事労務Q&A 〜育児休業給付金に上乗せで支給される出生後休業支援給付金〜2025/08/31
- 人事労務Q&A 〜育児短時間勤務をしたときに支給される育児時短就業給付金〜2025/07/31
- 人事労務Q&A 〜マイナンバーカードの健康保険証利用〜2025/06/30
- 人事労務Q&A 〜介護休業の対象となる家族と要介護状態の判断〜2025/05/31
- 人事労務Q&A 〜通勤手当を支給する際に考えておきたいルール〜2025/04/30
- 人事労務Q&A 〜就業規則変更手続きに必要な職員代表の適正な選出方法〜2025/03/31
- 人事労務Q&A 〜所定労働時間6時間以内のパート職員に対する休憩時間〜2025/02/28
- 人事労務Q&A 〜マイカーによる通勤途中の事故と医院の責任〜2025/01/31
- 人事労務Q&A 〜所定労働時間を変更した後に年次有給休暇を取得したときの賃金〜2024/12/31